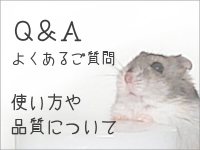化粧品の「本当のところ」
化粧水は効果ある?納得できる化粧水のハナシ
化粧水の効果の本音
化粧水の効果って何ですか?と聞くと「保湿じゃないの?」という声が聞こえてきそうですが、結論から先に言います。
化粧水の効果は「化粧水に使われている「水」以外の成分の効果」です。
???と思われるかも知れませんので、極端かも知れませんが例を挙げてみましょう。
次の化粧水があるとします。
------------------------
A:水と防腐剤だけでできた化粧水
B:水とヒアルロン酸と防腐剤でできた化粧水
C:水と、ニキビに効果がある植物エキスと防腐剤でできた化粧水
------------------------
ちなみに、どれも防腐剤が入っているのは、化粧水が腐らないようにするためです。
では、それぞれの化粧水の効果を考えてみましょう。
シチュエーションとしては、お風呂からあがっても少しすると顔がカピカピに乾燥する、という状況。
その状況でそれぞれを使用したときを考えましょう。
まずAですが、お風呂で散々水を浴びているのに風呂上りに乾燥する肌なわけですから、そこに水を塗っても意味がないですね。すぐにまた乾燥します。防腐剤の種類と配合量によっては肌に悪さだけしておしまいです。
ではBですが、こちらはヒアルロン酸がきちんと効く量で入っていれば、乾燥は防ぐことができます。ヒアルロン酸のメリットと、防腐剤のデメリットを天秤にかけて、ヒアルロン酸の保湿効果のメリットが勝てば、有益な化粧水といえます。
最後にCです。ニキビを防ぎたい人が使うならいいのですが、ニキビがなく乾燥が気になっているというシチュエーションですから、これはAと変わりません。乾燥は防げず、防腐剤のデメリットだけが残ります。
このように、化粧水の効果は、その化粧品にどんな効果を持った成分がどれくらいの量で配合されているかによって変わってくるわけです。
化粧品の効果の現実
化粧水の「水以外の成分」が効果を出しているといいましたが、次の問題は「水以外の成分」がどんな成分で、どれくらいの量が入っているかということになります。
「水以外の成分」の効果がその化粧水自体の効果だとすると、その成分に「期待したい効果」がないと化粧水を使う意味がない、もしくは防腐剤などのデメリットで肌にとってマイナス、ということになってしまいます。
ここで難しいのは、化粧品の世界は成分の配合量がほぼ非開示、ということです。
例えば先ほどのCの例で考えると、ニキビに悩んでいる人が、ニキビに効果がある植物エキスが入っているCの化粧水を選んだとします。
ところが実はその化粧水にはニキビに効果がある植物エキスが入っているものの、まったく効果の出ない微量でしか配合されていない、ということがあり得るからです。
そんなことあるの?と思われるかもしれませんが、これは化粧品の業界では当たり前に行われており、業界の用語では「微添(びてん:微量添加の略)」と呼ばれます。
今のところ、この効果の出ない「微添」化粧水に当たらないようにするには、美容成分の配合量を開示している稀な化粧水を探すか、お目当ての成分が医薬部外品の有効成分となっている薬用化粧水をチョイスするしかありません(医薬部外品の有効成分は配合量が定められていて、効果の出る量で配合されているのが保証されているため)。
化粧水に保湿を求めているときは?
一方、化粧水に最も求められていると思われる「保湿効果」についてはどうでしょう?
実際のところ、保湿剤が入っていない化粧水は探すほうが難しいです。
グリセリン、BG(ブチレングリコール)、ペンチレングリコールあたりのいずれかは、ほぼどんな化粧水にも入っています。
特にBG(ブチレングリコール)、ペンチレングリコールは抗菌作用も持っているので、頻用されている保湿剤といえます。
これらの保湿剤は化粧水のしっとり感を出すために使用されるのと、原料価格が安いため、上記のニキビの成分の例のように配合量を心配する必要はありません。
ただ、ヒアルロン酸よりはるかに保湿力が高く「スーパーヒアルロン酸」と呼ばれるアセチルヒアルロン酸、水で洗い流しても保湿力が落ちず、医療分野でも使われるリピジュア、ヒアルロン酸の5~10倍の保水力を持つといわれるサクランなど、グリセリンなどの安い汎用の保湿剤より効果が優れた保湿成分はいくつもあり、本当に乾燥肌をどうにかしたい、と考えている場合はそういった成分を配合している化粧水を探してみてもいいでしょう。
ただし安い化粧水は原料にあまりお金をかけていないので、「微添」化粧水を手にしてしまう可能性が高くなります。
求める成分が入っている化粧水を手にしても、きちんと求める効果が出ているか肌を観察しながら、化粧水を使用しましょう。
関連する記事
化粧品の乾燥小じわ(小ジワ)って何?【正直話】
乾燥による小じわを目立たなくするとは?
「乾燥による小じわ(小ジワ)を目立たなくする」というのは、2011年から化粧品で標榜できるようになった効能効果のひとつです。
もともと化粧品には効果としては表現していい内容が決まっています。
たとえば「うるおいを与える」「ハリを与える」「キメを整える」などの表現ですが、「しわ」に関する表現は認められておらず、それが2011年から解禁になった、ということです。
ちなみに化粧品で「たるみ」に関する表現はいまだにNGで、これについてはおそらく永久にNGのままでしょう。
「この化粧品はたるみに効きます」と広告表現していたらアウト!ということですね。
乾燥小じわに対する効能効果をうたうには?
ではこの「乾燥による小じわを目立たなくする」という効能ですが、どんな化粧品がそれを標榜できるのでしょうか?
たとえば「うるおいを与える」「ハリを与える」という効能効果については、それが事実であれば化粧品会社が自由に広告で表現できます。
しかし「乾燥による小じわを目立たなくする」については、ガイドラインに基づいた試験が必要で、その広告の書き方も「乾燥小じわに効く」など書き換えてしまうとNG、しかも「※効能評価試験済み」という文字を併記しなくてはならないなど、細かいルールがあります。
要はそういった試験を行い、結果が出たものだけが乾燥による小じわを目立たなくする」という効果をうたっている、ということになります。
実際に小じわに対する効果は?
ここまで「乾燥による小じわを目立たなくする」化粧品がどんなものなのかを書きましたが、最も気になるのは実際に効いてくれるのかどうかです。
結論から言いますと「小じわに対する効果は期待できるが、他の化粧品とそこまで差があるわけではない」というのが答えです。
というのも、この試験は20人~40人程度、1か月くらいで試験するのが一般的ですが、その方法は次のようなものです。
ーーーーーーーーーー
・目尻小じわで評価する。
・軽度のシワの女性で評価する。
・片側の目尻には試験品を塗り、もう片側の目尻には基本的に1か月間何も塗らない。(もしくは通常のスキンケアを行ったあと、片側の目尻だけに試験品を重ね塗りする)
・1か月後、左右の目尻のシワを比較する。
ーーーーーーーーーー
試験の内容によっては、1か月間、かたやスキンケアをしない目尻と、試験品を塗り続けた目尻を比較するわけですから、それは「試験品は効果あり」という結果が出やすくなります。
実際、筆者はこれまで11件の化粧品に対してこの試験を行ったのを見てきましたが、効果が認められなかったのはそのうちのたった1件でした。
要は、試験をすれば、ほとんどのスキンケア化粧品は効果が得られる試験だといえます。
じゃあどんな化粧品でもやってしまえばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、この試験は1件200万円ほどの費用がかかるので、エイジングケア感をより強く打ち出したい、とか、ブランドの中で美容液に特別感を出したいので効能効果を追加したい、というときに行われているのが実際かと思われます。
化粧品でシワをどうにかしたいなら
ここまでお話ししたのは「乾燥による小じわ(小ジワ)を目立たなくする」という化粧品についてですが、一方、医薬部外品には「シワを改善する」という効能効果を持ったものがあります。
医薬部外品とは「薬用化粧品」とも呼ばれるもので、医薬品と化粧品の中間に位置するものですが、この「シワを改善する」という効能効果を持った医薬部外品は、化粧品の「乾燥小じわ」とは効果のレベルが違います(そのかわり価格もだいぶ高めのことが多いですが…)。
詳しい話はまたどこかでお話しできればと思いますが、シワに効く化粧品を使いたいと考えていらっしゃいましたら、医薬部外品で「シワを改善する」という効能効果を持っているものを選ぶか、「乾燥による小じわ(小ジワ)を目立たなくする」とか「シワを改善する」といった効能効果を標榜していないけど、成分から考えて、シワに対する効果が期待できる化粧品を発掘するのがおすすめです。
関連する記事
原液化粧品の定義と罠【プチ閲覧注意】
原液化粧品の定義
まず、おかたい話ですが「原液化粧品」とは何でしょう?
その定義は何でしょう?
ずばり言ってしまうと、一般的に「化粧品原料をそのまま容器に詰めただけの化粧品」を「原液化粧品」と呼びます。
化粧品は様々な化粧品原料を混ぜて、それを水や油に溶かして、ローションやクリームにしています。これは視点を変えると、美容成分の化粧品原料を水や油で薄めている、とも言えます。
「美容成分を薄める」というと何だか効かなくなるようでイメージがよくないですが、美容成分の化粧品原料に関わらず、ほとんどの化粧品原料は、そもそも何%くらいに薄めて使うとちょうどいい効果が出る、ということを想定して作られています。
例えば化粧水に1%の濃度で配合することを想定している植物エキスがあるとします。
これをもし薄めないで100%で塗ったら、次の日には肌が真っ赤になって皮膚科行き、なんてことは高確率でありえるケースです。
「原液化粧品」とは、そういった危険性のない化粧品原料について、水や油で薄めることなく、最高の美容効果で使えますよ、という化粧品ということになります。
蛇足ですが、原料と原料をそのまま混ぜただけ、というもの「原液化粧品」の定義のなかに入ります。
「3つの原料を混ぜただけの原液化粧品です」といったケースですね。
要は「原料を薄めずそのまま使っている」というのが「原液化粧品」の定義のだいじなところと言えます。
原液化粧品の罠
そう聞くととても効果がありそうで魅力的に見える「原液化粧品」ですが「化粧品原料をそのまま容器に詰めただけの化粧品」という定義を逆手に取っている原液化粧品が存在しているのも事実です。
それは、化粧品メーカーのために、原料会社がそもそもカスタマイズした原料を販売しているケースです。
先ほどの例でいうと、本来化粧水に1%で配合する「植物エキスA」を、原料メーカーのほうで100倍に薄めて「植物エキスA´」というものをつくります。
化粧品メーカーはそれをそのまま容器に詰めて「植物エキスA原液」として売り出します。
これは極端な例ではありますが「そんなことあるの?」と思われるかもしれません。
しかし化粧品メーカーと原料メーカーのつながりは強く、あるたったひとつの商品に独自性を出すために、原料メーカーが化粧品メーカーのために原料をカスタマイズするということは、よくあることです。
定義として「原料を薄めていないよ」というのが化粧品メーカーのいう「原液化粧品」なわけですが、そもそも原料メーカーのほうで薄めている、というケースがあるわけです。
見極めの難しい「原液」という言葉
そこまで聞いてしまうと、原液化粧品に興味のある方は「じゃあどうすればいいの?」と思われるかもしれません。
しかし原液化粧品の見極めはプロが見ても困難です。
逆に、スクワラン、ホホボオイル、アルガンオイルなど、オイル系原液化粧品は全成分を見れば簡単にわかります。
化粧品に使われるオイル原料は100%のものがほとんどで、追加で入っていても酸化防止剤のトコフェロール(ビタミンE)くらいなので「スクワラン原液」と言っていて全成分に「ミネラルオイル、スクワラン」と書いてあったら「ウソでしょ?」とわかります。
スクワラン原液には「スクワラン」しか表示されないはずです。
しかしオイル系ではない、要は「水」が入ってくる原液化粧品は、キーの美容成分の配合量が想定できないことが多く、判断が難しいです。
例えば「ヒアルロン酸原液」というものがありますが、ヒアルロン酸はそれ自体液体ではなく個体なので「ヒアルロン酸原液」というものはヒアルロン酸を水に溶かして加工した、化粧品用の「ヒアルロン酸溶液」という原料なわけです。
これは全成分を見ると「水、ヒアルロン酸、フェノキシエタノール」(フェノキシエタノールは防腐剤です)みたいに書かれているので「いったいヒアルロン酸は何%なの?」というのがまったくわからないのです。
こうなるともう、ブランドの信用力と、価格が変に安くないか、というところでしか判断できません。
ただ、水が入っている原液美容液の中で、これは信用できるだろう、という指標はあるにはあります。
それは、全成分の最初の成分に「水」ではなくキーとなる美容成分が書かれている原液美容液です。
最初に美容成分が書かれているということは、水より美容成分の配合量が多いということになり、美容成分の配合量が保証されているといえます。
今、流行りの幹細胞コスメですが、幹細胞コスメに使われている「幹細胞培養上清液」という原料は、製造方法的に、薄めなければ原材料の表示に「水」は入ってきません。
ただ、さまざまな原料メーカーから販売されている幹細胞原料の中で、水で薄められていない(成分表示に「水」が出てこない)原料は、数えるほどしかありません。
もし全成分に「水」の記載がない幹細胞原液化粧品があれば買い、と判断できますが、全成分の最初に「水」の記載がある場合には、やはりブランドの信用力と価格、そして使ってみての効果で判断していくしかないのでしょう。
関連する記事
ボタニカルシャンプーとは?髪と地肌にいい?【本音編】
ボタニカルシャンプーとは?
最近よく聞く「ボタニカルシャンプー」。
ボタニカルシャンプーとは、そもそも「ボタニカル」とは何でしょう?
「ボタニカル」とは「植物の、植物性の」などの意味であり、化粧品においては「植物性の」「植物由来の」といった意味で使われています。
よって「ボタニカルシャンプー」というと、単純に「植物性のシャンプー」「植物由来のシャンプー」ということになります。
一般的にシャンプーやトリートメントなどヘアケア化粧品には、洗浄や髪の仕上がりのために、界面活性剤やシリコーンなど、ケミカル(化学合成)的な成分が多用されます。
シリコーンを配合しない「ノンシリコーンシャンプー」が流行したのはこういった背景があり、より「ナチュラルなヘアケア化粧品です」というマーケティングが成功した事例ともいえますが、同じようにマーケティング視点で見ると「ボタニカルシャンプー」もその延長線上にあるものかもしれません。
要は「ケミカルな成分を減らしました」というものから「さらに植物でつくりました」にグレードアップされた、ということですね。
だけど野放しの「ボタニカル」
しかし「ボタニカル」という化粧品の訴求には現状、大きな問題があります。
それは「ボタニカル」という言葉が「植物性の、植物由来の」という意味しか持っていないため、かなり自由に使えてしまう、ということです。
簡単にいってしまうと、100%植物由来成分でつくったシャンプーでも、たっぷりシリコーンも配合して1%しか植物由来成分を入れていないシャンプーでも、どちらも「ボタニカルシャンプーです」と言えてしまえる、ということです。
日本の化粧品は「オーガニック」という言葉の使用についても曖昧ですが、「ボタニカル」は極端に言えば「植物由来の成分を配合していれば使える」という、さらに使いやすい言葉なので、「ボタニカルシャンプー」といわれても、実際には化粧品の成分がある程度わかる人でないと、本当にボタニカルシャンプーといえるシャンプーなのかは判断ができません。
ここではひとつだけ簡単な判断の仕方をお教えします。
「医薬部外品」と書かれていないシャンプーの全成分表を見て、上から5成分くらい以内に「~メチコン」という成分(この名称はシリコーンです)があったら、「ボタニカルシャンプーと謳っているけれど他のシャンプーと変わらない」と考えていいでしょう。
「ボタニカルシャンプーです」=「ナチュラル系です」とアピールしているのに、シリコーンをしっかりと配合している商品であれば、そのポリシーはあまり信用できません。(ただし、シリコーンは髪にも頭皮にも悪い成分なわけではないので、そこは誤解のないようにお願いします)
あと、本当に植物由来成分だけでシャンプーを作ろうとすると、非常にコストが高くなり、商品代としては通常のシャンプーの倍以上になってくる可能性が高いです。
他のシャンプーとさほど値段の変わらないボタニカルシャンプーは、あまり「ボタニカルしていない」可能性が高いと考えてよいでしょう。
ボタニカルシャンプーは髪と地肌にいいの?
ボタニカルシャンプーというけれど、結局、髪と地肌に良いの?というところがもっとも興味のあるところです。
ですがこの質問に対する答えは「わからない」です。
シャンプーの効果として、髪にとってよいことは、しっかりと成分がキューティクルを補修してくれて、なめらかな髪を保ってくれる、といったことでしょう。
一方、地肌によいことは、洗浄はしてくれるが脱脂しすぎない、界面活性剤などが残らない、ついでに美容成分がスキンケアをしてくれればなおよし、といったところです。
ここまで聞くと気づくかもしれませんが「ボタニカルシャンプーである」=「植物由来のシャンプーである」というだけで、この髪と地肌に対する好ましい効果を備えているシャンプーなのかどうかは、判断ができないのです。
ボタニカルシャンプーに興味のある方は、おそらく今使っているヘアケア化粧品に何かしら不満があって他のものを探しているのでしょうから、ボタニカルシャンプーは選択肢のひとつとしてあってよいと思います。
ただし「ボタニカルだから良い」のではなく「ボタニカルと標榜するからには、何かしら髪や地肌のことを気にしている商品なのだろう」という考え方で、ボタニカルシャンプーを手に取ることをおすすめします。
関連する記事
化粧品の成分の見方と、見破り方【後編】
成分表の1%ラインの見つけ方
では次に、1%ラインのおおまかな見つけ方についてお話しします。
(【前編】に書きましたが、あくまで医薬部外品の記載の方法は別のルールとなりますので、参考にしないでください)
①:コラーゲン、ヒアルロン酸や〇〇エキス
「何か美容に良さそう」といったこういう成分ですが、ほとんどの場合1%は入っていません。
(かといって、1%も入っていないから効果がない、というわけではないので、そこは誤解しないでください)
一方、化粧品メーカーとしては順不同であれば、これら美容に効きそうな成分の表示をなるべく上のほうに持ってきて目立たせたいと考えます。
だから、もし5番目に〇〇エキスがあったら、4番目までが1%以上の成分、と予想できます。
美容効果がありそうな成分が成分表のずいぶん上のほうに記載されている場合は、こういった事情があると認識しておいたほうがいいかもしれません。
「上のほうにヒアルロン酸が書いてあるから効きそうね」なんて思ってはいけません。
1%以下なら5番目に記載されていようが30番目に記載されていようが、変わりはありませんので…。
②:ポリオール系成分
ちょっと難しい話になりますが、こちらは主にスキンケア化粧品に関する話です。
化粧水やクリームにはよくBG(ブチレングリコール)、ペンチレングリコール、ヘキサンジオールといった成分が使われています。
これらは似た成分ですが、しっとりだけどベタつかないテクスチャーを演出でき、保湿効果があり、かつ防腐効果が期待できるので、頻繁に化粧品に使用されています。
BGについては10%程度まで配合されることがありますが、ペンチレングリコール、特にヘキサンジオールはこの1%ライン付近の配合量で使用されることが多いです。
①のように成分表の上のほうにエキスや美容成分が見つからない場合は、これらポリオール系の成分がどこにあるかを見て1%ラインを想定する、というやり方があります。
例えばヘキサンジオールが5番目にあれば、そこまでが1%かな、という想定。4番目にペンチレングリコールがあり、20番目にヘキサンジオールがあれば、ペンチレングリコールまでかその次くらいまでが1%で、ヘキサンジオールは1%以下だな、とういう判断になる感じですね。
例えば、ナイアシンアミド
シワへの効果が注目されている美容成分、ナイアシンアミドですが、こちらを例に挙げてみましょう。
ナイアシンアミドは3%ほど配合すると有効とされていますが、もちろん0.001%しか配合しなくても全成分には表示できます(効果があるかは知りませんが…)。
化粧水Aは全成分に「水、グリセリン、ナイアンシンアミド、BG、ペンチレングリコール…」とあり、値段は100mlで4,500円、広告にも「ナイアシンアミド配合!」と大きく出ています。
そうすると「全成分から見るとまあBGより上にあるから、ナイアシンアミドはきちんと3%くらい入っているのかな、価格も高いから原料のコストもかけていそうだしね」と判断できます。
しかし一方、化粧水Bは「水、グリセリン、BG、ペンチレングリコール、コラーゲン、○○エキス、ナイアシンアミド…」と書かれていて、価格は1,500円、さらに300mlの大容量で、おまけにそこそこ豪勢な容器に入っていたりします。
これで「ナイアシンアミド配合!」と書かれていても「ちょっと待てよ?」となってしまいます。
コラーゲン以下は1%未満と考えられ、それは0.9%かもしれないし、0.0001%かもしれません。
そして価格は低く、容器にもコストがかかっているとすると、原料にはコストがかけられません。
ついでに大容量なら、美容成分はさらに薄まって入っている可能性が大です。
結果「いったいナイアシンアミドの配合量はどれくらい?」という疑問がわいてしまいます。
本来はしっかり美容成分の配合量が書いてあればいいのですが、そういった化粧品は稀です。
また化粧品の成分の配合量はコールセンターに電話したところでまず「企業秘密です」と教えてもらえません。
そうしたとき、面倒ではありますが、こうした方法で何となくでもその化粧品を判断する、という方法があることは、憶えておくのも得かもしれません。
関連する記事
化粧品の成分の見方と、見破り方【前編】
化粧品の成分記載のルール
まず基本のところですが、化粧品の成分表を見ようとするときはその表示の見方のルールを知る必要があります。
ざっくりと言ってしまうと、ルールは以下の2点です。
・配合量の多いものから順に記載する
・配合量が1%以下のものは順不同でよい
ちなみに「医薬部外品」と書かれているものは化粧品と表示のルールが違うので、それはまたどこかでご説明します。
実は成分表に記載されている成分の大半は配合量が1%以下の成分であり、順不同に記載されているので、成分表の見方といってもあまり細かく見る必要はありません。
むしろどういったポイントを見れば、どういったことがわかる、ということを知っているほうが役に立つでしょう。
1%以上の成分は何を表す?
きちんと配合順に書かれている1%以上の成分ですが、実は1%以上の成分は数的には少なく、少なければ3成分、多くとも10成分くらい、平均すると4,5成分あたりしかないと考えてください。
1%以上配合されている成分は成分表示の1番目からだいたい5番目程度まで、ということです。
1%以上の成分はその化粧品の基剤(ベース)となる部分ですが、ここを見ることでその商品のコンセプトが想像できます。
例をいくつかあげましょう。
★クリームの成分の上位のほうに、ポリマー(~ポリマーという表示)やシリコーン(~メチコンという表示)があれば、使用感、テクスチャー重視、それでもし1,000円程度の価格のものなら、コスト面から美容成分はほとんど入れることができないので、使ったときには気持ちがいいけれど長期間続けても肌にいいことはないかもしれない。
★同じような表示があり、シリコーンが表示の上位にきているようなトリートメントであれば、髪表面のコーティングに重きを置いているので、サラサラな仕上がりにしたい人には向いているかもしれない。
★化粧水の成分で一番上の成分が「水」ではなく「温泉水」となっていたら、まじめに作られている温泉水コスメ。
★逆に「温泉水配合化粧水」と大きく広告していても成分を見たとき「水、グリセリン、BG、温泉水…」のような感じになっていると、温泉水は入っていてもせいぜい数%なので、なんちゃって温泉水コスメ。
…という感じです。
特に、どういう広告や訴求をしているのか、また価格はどうか、と合わせて全成分表示を見てみると、おかしな言い方ですがその化粧品の「誠実度」が見えてくることがあります。
関連する記事
化粧品のキャリーオーバー成分ってなに?
化粧品のキャリーオーバー成分とは?
化粧品の「キャリーオーバー成分」。
正直、化粧品や食品の業界にいるか、よっぽど化粧品マニアでいろいろと調べている人しか知らない言葉なのではないかと思います。
では、化粧品のキャリーオーバー成分とは何でしょう?
正確な言い方ではないですが、わかりやすくひとことで言えば、化粧品でいうところのキャリーオーバー成分とは、化粧品に配合されているけれど微量なので成分表に書かれていない成分のことです。
化粧品はすべての成分をパッケージに表示することが原則となっていますから、キャリーオーバーについてはその例外ということになります。
キャリーオーバーとなるには
では、どういった成分がキャリーオーバー成分になるのでしょうか?
宝くじで「キャリーオーバー」というと「繰り越し」という意味で、前回の賞金がくっついてくる、という意味ですが、キャリーオーバー成分も同様の意味で「主成分にくっついてくる成分」という意味です。
具体例をあげましょう。
1%の配合量で効果を発揮する防腐剤Aがあります。
Bという植物エキスがあり、この植物エキスBには腐らないようにするためにAが1%配合されています。
あるローションを作るとき、植物エキスBをローションに1%の濃度で配合しました。
そうするとローションの中には、1%の1%で、0.01%のAが含まれていることになります。
ローション全体から見ると、Aは0.01%しか入っていません。
本来1%で防腐効果を発揮するのに、1/100しか入っていないので防腐剤としての効果はない、ということになり、この場合キャリーオーバー成分として、成分表には防腐剤Aを記載しなくてもよい、ということになります。
キャリーオーバー成分の問題点
上記のケース以外にも、不純物として含まれる微量な成分もキャリーオーバー成分として表示されないこともありますが、化粧品のキャリーオーバー成分についてはいくつかの問題点があります。
まずひとつは、キャリーオーバー成分として、表示したくない成分を隠される可能性がある、ということです。
どこまで微量の配合であればキャリーオーバー成分として表示しなくてよい、といった規則はなく、キャリーオーバー成分として表示しないかどうかの判断は化粧品メーカーの裁量次第です。
業界としては、ノンパラベン、パラベンフリー(パラベンという防腐剤を使っていないというアピール)をする場合には、キャリーオーバーにもパラベンを含んでいてはいけません、という通知を出したりしていますが、それ以外に目立った規制はありません。
キャリーオーバー成分は「表示してはいけない」ではなく「表示しなくてもよい」成分ですので、キャリーオーバーだろうがなんだろうがすべての成分を表示する、というスタンスの化粧品メーカーもありますし、ほとんどの化粧品メーカーはキャリーオーバーの制度を悪用しようとは考えていませんが、たとえばキャリーオーバーの制度を使って、化粧品の成分をよりナチュラル寄り(天然由来寄り)に見せる、肌にやさしそうに見せる、ということは可能です。
また、肌に合わないことがわかっている成分などがある場合や、使いたくない成分がはっきりしているという場合、本当にその成分を避けるにはキャリーオーバー成分の有無を確認しなくてはならないので、その点にも注意が必要です。
関連する記事
ファンデーションの選び方【実践編】
何ファンデーションを選びますか?
クリーム、リキッド、クッション、プレスト、ルースパウダーとファンデーションにもいろいろありますが、まずはどんな剤形のファンデーションを選ぶかを考えます。
成分面からみると、これらのファンデーションは大きく2つに分かれます。
①:水、オイル、粉体からできているもの
クリーム、リキッド、クッション、湿式のプレストタイプが該当します。
クッションはスポンジにリキッドファンデーションをしみ込ませたものなので、実質的にはリキッドファンデーションと考えてください。
これらは単体でも仕上がりがよく、長持ちするので、化粧下地を使わないのであればこういったファンデーションを使うのがいいでしょう。
②:主に粉体でできているもの
ルースパウダーやプレストパウダーが該当します。
成分的に見ると、肌に負担をかけにくいものが多いです。
薄付きメイクでよくて、肌への負担も減らしたい、というのであれば化粧下地なしで②を使うのもいいかもしれません。
ファンデーションのスペックを見る
次にファンデーションのスペックを見ます。
①:SPF、PA
UVカット機能があるかどうかです。
現在、紫外線による影響のほうが加齢より肌老化にとって悪いという認識が一般的です。
要は、UVカットがあるかどうかでシミ、シワができやすくなるかどうかが変わってきます。
化粧下地にUVカット効果がある場合はいいですが、化粧下地にUVカット効果がない場合やそもそも化粧下地を使わない場合は、ファンデーションにUVカット効果があったほうがいいです。
SPF、PAは高ければ高いほどいいですが、少なくともSPF30、PA++くらいの値はほしいところです。ちなみにそれぞれの最高値はSPFが50+、PAが++++です。
ざっくりというと、SPFが高いほどシミが防げ、PAが高いほどシワが防げると考えてください。
②:ノンケミカル・紫外線吸収剤不使用
「ノンケミカル」と書いてあるか「紫外線吸収剤不使用」と書いてあるほうが、肌にやさしめ、と考えてください。(「ノンケミカル」と「紫外線吸収剤不使用」は同じ意味です)
UVカット効果を出すために「紫外線吸収剤」という成分を使うことがあります。
紫外線吸収剤を使うと、使用感がよく、UVカット効果が高い化粧品を作ることができますが、肌が弱い人には刺激がある場合があります。
肌が弱い人はSPF、PAが高いことより、ノンケミカル・紫外線吸収剤不使用であることを優先したほうがいいでしょう。
③:石けんオフ
乾燥肌の方、敏感肌の方はできるだけクレンジングを避けたほうがいいので「石けんで落とせる」と書かれているファンデーションを選んだほうがいいです。
ただ化粧下地がクレンジングが必要なものの場合、ファンデーションだけ石けんオフにしても意味がないので、化粧下地を使う場合はその点も気をつけましょう。
あと「石けんオフ」はメーカーの基準によるので「石けんで落とせます」と書いてあっても、使う石けんの種類によって落ち切らない場合があります。
石けんでオフできているかどうかは、実際に使ってみて最終判断しましょう。
シリコーンやポリマーで機能を予想
ファンデーションに使用されるシリコーンやポリマーは、使用感を良くするのとメイク持ちを長くするのに重要です。
ですがこれらの成分が多くなると、どうしてもメイクオフするのにクレンジングが必要になってきます。
ですから、テクスチャーや持ちがいいファンデーションを選びたければシリコーンやポリマーが多く使われているファンデーションを選べばいいですし、仕上がりより石けんオフを重視したければ、それらの成分が少ないファンデーションを選べばいい、ということになります。
とても大雑把なやり方ですが、化粧品の成分表示から、シリコーンやポリマーがどれくらい使われているのかを想定する方法があります。
化粧品の成分表示は、1%以上の成分は配合量が多い順に記載することとなっていますので、記載順の上から3,4番目くらいまでにシリコーンやポリマーの成分名称があれば、比較的シリコーン、ポリマーが多いファンデーションと考えられるでしょう。
「~ジメチコン」という成分名がよく見られますが「~メチコン」という言葉があればシリコーン系成分、ポリマーはその名のとおり「~ポリマー」「~コポリマー」「~クロスポリマー」という名称で記載されていることが多いです。
当然、どんなシリコーンやポリマーが使われているかで使用感やオフのしやすさは変わってきますが、ファンデーションを買う場合にひとつの指標として見てみるのもいいかもしれません。
関連する記事
肌断食とは?肌断食と化粧品の関係のホンネ
肌断食は肌にいい?
クレンジング、メイク、日焼け止め、化粧水やクリームまで、化粧品をすべてやめてしまって肌を本来の自然な状態に戻そうという『肌断食』。
メイクだけをやめたり減らしたりするだけのライトな肌断食もありますが、肌断食は肌にとって良いのでしょうか?
その問いへの答えは、こんな感じです。
肌に悪い化粧品を使っている、もしくは化粧品の使い方がまちがっている人にとっては、肌断食は肌にいい。
肌にいい化粧品を使っている人にとっては、肌断食は肌に悪い。
肌断食とは「今使っている化粧品をやめること」です。
もともと化粧品を使っていない男性には、肌断食はできません。
肌断食をしてみようかな…と考える人には当然今使っている化粧品があります。
ということは、肌断食をして今よりも肌がよくなるか悪くなるかは、今使っている化粧品抜きにして語れないのです。
化粧品と肌断食の関係
肌断食をして目指す肌を「健康な素肌」とします。
そうすると
不健康な素肌 < 健康な素肌 < 健康以上のきれいな素肌
となります。
これは言い換えると、次のようになります。
化粧品荒れ < 肌断食 < 化粧品美肌
メイク品できれいになる、という話は置いておいて、化粧品を使うことによって素肌に起きる良い面と悪い面から、肌断食のメリットとデメリットを考えてみましょう。
肌断食のデメリット
肌断食を始めて、乾燥肌に耐え、数か月を経てやっと化粧水などを使わなくても大丈夫な健康な素肌を手に入れたとします。
ですが健康な素肌に戻っても、当然、老化現象が止まるわけではありません。
シミやシワが増えてきますし、黄ぐすみで全体の顔色のトーンも暗くなってきます。
これに対して、化粧品を使う大きなメリットは次のとおりです。
・UVカットによる抗老化作用
現在、化粧品業界では加齢よりも紫外線のほうが肌の老化を進行させている、という認識が高くなっています。
ですから、日焼け止めやファンデーションによるUVカット効果は、肌の老化防止に有効、ということになります。
・美容成分による美容効果
美容成分が効果の出る量できちんと配合されていれば、加齢によって生じてくるシミやシワ、黄ぐすみの予防や改善が期待でき、抗酸化作用のある成分が入っていれば老化防止の効果が期待できます。
「美容」とは「健康以上にきれいになろう」ということですが、この「美容」を手放すことが肌断食のデメリットといえます。
肌断食のメリット
化粧品はさまざまな成分の組み合わせでできていますが、その中には本来肌に必要のない成分もたくさん入っています。
防腐剤や安定化剤などは、化粧品を腐らなくするためや、化粧品に沈殿が出たり分離したりするのを防ぐには必要ですが、肌にはまったく不必要なものです。
そういった成分が肌に悪い影響を与えるのかどうかは、成分の種類や配合量、使う人の体質によりますが、悪い影響のほうが美容効果によるメリットを上回っている場合、化粧品を使えば使うほど肌は体力を失っていきます。
化粧水や美容液を使っていれば安心、という人もいますが、化粧品は何でもいいから使っていればいい、というものではありません。
極端な例ですが、例えば100円の化粧水には美容成分はほとんど入っていないでしょう。
でも防腐剤はしっかりと入っているはずです。
また、クレンジングなどによる肌の脱脂のしすぎも、乾燥肌から肌トラブルを招きます。クレンジングは「メイク品を落とすことができる」=「メイクをすることができる」ということだけがメリットで、クレンジングを使うことの「肌へのメリット」は本来ひとつもありません。
『肌断食』という言葉が生まれたのはまさしくこういった「化粧品害」が根本にあり、肌断食のメリットは「美容」を捨てても「化粧品害」を避けて「健康」を選択できる、ということでしょう。
ここまで肌断食のメリット、デメリットを化粧品に絡めてお話ししてきましたが、実際にはやってみないとどうなるかわかりません。
人の肌質はあまりにも複雑で、肌断食をしたときにどういったことが起きるのかはおそらく専門家でも予想ができないものでしょう。
もし肌断食をやってみたい、というのであれば、メイク品をクレンジング不要のものに変えてみる、そのあと、ベースメイクをやめてみる、基礎化粧品では、アイテムを1品減らしてみる、そのあと、朝晩使っていたものを晩だけにする、といったように、肌の様子をしっかりと観察しながら、段階を経ていったほうがリスクは少ないでしょう。
肌断食が本当にあなたにとって良いことかどうかは誰にもわかりません。
あなたにとって、最もよい肌との付き合い方が、見つかりますように。
関連する記事
クレンジングの選び方【簡単編】
クレンジングの選び方の結論
オイル、バーム、リキッド、クリーム、ジェル、ミルク、拭き取り…いろいろあって迷ってしまうクレンジング選び。
でも結論からいうと、どのクレンジングがいちばんいい、ということはありません。
というのは、人によって使っているメイクはライトメイク、ハードメイク、ほぼすっぴん、とさまざま。さらに肌の皮脂量や、乾燥の具合も人それぞれだからです。
じゃあどうやってクレンジングを選べばいいの?という話ですが、ポイントとしては次の3点を気にしてください。
①:自分の使っているメイクがきちんと落とせる。
(肌にメイクを残したくないので、これは基本です)
②:そのうえで、クレンジングのあとに肌がつっぱらない。
(肌がつっぱるのは脱脂しすぎている証拠。皮脂まで落として乾燥肌を助長し、ひいては肌の老化の加速につながりかねません)
③:そのうえで、使い終わったあと、肌がヌルヌルしない。
(メイクが落とし切れていないか、クレンジングに含まれる油分、洗浄剤である界面活性剤が落ち切っていない可能性があります)
実際のところ、③はあまり気にする必要がなく、②のように肌がつっぱっている方がほとんどでしょう。
ですから目指すところは、メイクをしっかりと落としながらなるべくつっぱらないクレンジングを選ぶ、ということになります。
クレンジングの種類は気にしない
オイルクレンジングの特徴はこう、リキッドはこう、敏感肌には…といった情報もあふれていますが、必ずしもそういったクレンジングの種類から入る必要はありません。
クレンジングは基本的に「油分でメイクを溶かす」「界面活性剤の作用でメイクを肌から落とす」という2つの作用でクレンジング効果を発揮しますが、クレンジングに使われている油分も界面活性剤も非常に多くの種類があります。
ですから、例えば同じクレンジングオイルでも、A社とB社では使っている油分や界面活性剤の種類も、その割合もさまざまで「クレンジングオイルだから…」という話はあまりあてにならないのです。
しいていえば、拭き取りクレンジングは物理的に肌をこするので気をつけたほうがいいということと、オイルやリキッド、ミルクのように液体のクレンジングなら、手のひらで水を加えて薄めて、クレンジングの強さをコントロールできるので勝手がいいかも、ということくらいでしょうか。
クレンジングのちょっとした知識
あと、クレンジングについて知っておいたほうが便利かな、と思われるものをいくつか。
・美容成分はあまり気にしない。
基本的に洗い流してしまいます。中にはそれでも効果を発揮する成分もありますが、クレンジングにどんな美容成分が入っているかはあまり気にしなくていいでしょう。
・濡れた手でも使えるクレンジングには注意。
お風呂で使えるクレンジングも同じかもしれませんが、水が入っても洗浄力が維持できるように界面活性剤の量が多めです。脱脂力が強いので注意です。
・安いクレンジングオイルは脱脂力が強い。
安いクレンジングオイルは、ミネラルオイルなど原料費のかからない石油由来のオイルをベースにしていることが多いです。
石油由来だから悪いわけではありませんが、これらのオイルは脱脂力が強いので、同じように注意が必要です。
・ホイップ=リキッド。
クレンジングホイップというものがありますが、クレンジングリキッドにメッシュをかけて泡状にしているので、基本的にはクレンジングリキッドと同じと捉えてかまいません。
自分にあったクレンジングを見つけるにはいろいろと試してみるしかありませんが、間違ったクレンジングを使い続けると乾燥肌がいつまでも治らず、ひいては肌の老化を早めます。
これがクレンジングの最大のリスクです。
化粧水や美容液を変えたら肌が変わった!と同じように、クレンジングを見直したら肌が変わった!となったら、うれしくありませんか?
洗い流すものだから、とおろそかにしないで、クレンジングには化粧水や美容液と同じレベルで気を使いましょう。
関連する記事